第10回読書会 堀辰雄「菜穂子」
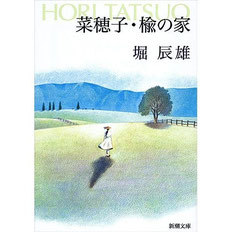
堀辰雄「菜穂子」読書会(抄)
日時:2013年8月7日(水)15:30~17:00 岡山オフにて
場所:ホテルグランヴィア岡山1F ロビーラウンジルミエール
参加者:6、イコ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イコ:では「菜穂子」の読書会を始めましょうか。
6:ケーキが来てからでもいいですけどね。
◆悲劇をナルシスティックにとらえる
イコ:どうでしたか、堀辰雄。
6:僕はあまり好きじゃないんですよね。
イコ:あ、そうなんですか。
6:これは一見、僕好みの小説に思われるかもしれないんですけど、悲劇をナルシスティックにとらえている感じがあまり好きになれません。
イコ:ああ、そういうところはあるかもしれませんね。堀辰雄はサナトリウム(結核患者のための療養所)っていう、日常と切り離された特別な場所をよく使うけれど、場所設定自体が、悲劇性を帯びている。
6:そういう場所で孤独に生きている私たち、みたいな。
イコ:「風立ちぬ」では、結核患者と付添いの夫が、いっしょにサナトリウムで暮らしながら、死のかげで生きることに幸せを感じるといった内容でした。
◆心理のための風景
イコ:6さんはHPの部員名簿でも述べておられるように、風景描写がお好きやと公言しておられますが、この小説の風景描写はダメだった?
6:うーん、僕の好きな風景描写と違うんですよね。「菜穂子」は登場人物の心理にスポットを当てた作品です。だから、描かれる風景もすべて、心理のための風景になっているんです。僕が好きな風景描写は、風景のための風景なんです。
イコ:詳しく教えてください。
6:堀辰雄の場合は、風景よりも、登場人物の心理が先に来るんです。「孤独」とか「さみしさ」といった感情が、風景に反映される。
イコ:なるほど。作中に何度も出てくる、「立ち枯れた木」はまさにそうですよね。菜穂子の感情が、そういう風景を見せている。6さんがよく話題に出される磯崎憲一郎などは、そうではないんですか?
6:磯崎憲一郎は、まず風景なんです。人物の感情も描かれるんですけど、それは風景とは独立している。
イコ:自分は少し違う考え方をしています。磯崎の風景は、たしかに独立しているようだけれど、たとえば「終の住処」では、ずっと月がのぼったままになっているとか、ふつうでは考えられないような風景が次々にあらわれますよね。あれって、登場する人間の見ている風景というか、人間の心理に従属した風景なんじゃないでしょうか。
6:そうですね。シンボルとアレゴリーの違いなんじゃないかな、と思います。堀辰雄の作品の場合は、すでに一般化された感情、たとえば「孤独」や「さみしさ」のようなものを、風景が象徴している。磯崎憲一郎の作品は、風景が物語の中で、意味をもってくる。他の作品では通用しないかもしれないけれど、磯崎作品のみで意味をもつような風景です。
イコ:なるほど。堀辰雄は、風景に何かの意味を当てはめようとしているところが強いですよね。
6:僕が好きなのは、シンボルとしての風景よりも、もっと風景が強い作品です。ル・クレジオの作品とか、そうじゃないでしょうか。
イコ:たしかに。
6:神の視点があまり好きじゃないっていうのもあります。堀辰雄は、トルストイの「アンナ・カレーニナ」に影響を受けて「菜穂子」を構想したようですが、僕は、トルストイも好きじゃないんですよね。バフチンが『ドストエフスキーの詩学』で、ドストエフスキーとトルストイを比べていたんです。それによるとトルストイの作品では、作者が小説の神として君臨しており、すべてのものの裏で糸を引いてるんです。トルストイは登場人物を操り人形にしてしまう。それに対してドストエフスキーは、作者も作品の一登場人物に過ぎないというか。色々な考え方をもつ人が出てきて、作者もひっくるめて、自由勝手に動く。ポリフォニーですね。
イコ:なるほど。
6:僕は、堀辰雄はトルストイほどじゃあないと思っていて、だから、トルストイほど嫌いじゃないです。でもガルシア=マルケスなんて、トルストイ以上に、作者の力がものすごいじゃないですか。人物は自分で勝手に動いているように見えても、ぜんぶ周到に作者が操っているような気がする。だから僕は、ガルシア=マルケスを埋葬したいんです(笑)
イコ:埋葬(笑)
6:同じラテンアメリカでも、バルガス・リョサは違う気がします。あの人は語りの強さがあります。
◆他者が描かれている
イコ:自分も堀辰雄の作品は、そんなに好きってわけじゃないんです。今回読書会のために、以前読んだ「風立ちぬ」を再読してみたんですけど、見事に忘れていた(笑)
6:そうなんですか。
イコ:宮崎駿監督の「風立ちぬ」を観て、そういえば、あのシーン使われてたなあ、と少し思い出したくらいで。再読して、忘れた理由が分かりました。きれいにまとめられすぎというか、悲劇性が強調されすぎて、あんまりおもしろくない。重病の女がまずいて、男がそれに付き添ってる。男は女の死後に別荘を訪れて、けっこう長いページを割いて、いわゆる「喪の儀式」みたいなことをやってる。「セカチュー(世界の中心で愛を叫ぶ)」と同じことやってるなあと思ったんですけど、そういうのは鼻白んでしまいます。それに比べると、「菜穂子」はずっとおもしろく読めました。
6:どうしてですか。
イコ:色んな人間が出てくるんですよね。その人間も、それぞれ色んな考え方をもってて、ちゃんと小説の中に立っている感じがある。小説が一人の自我の中に完結していなくて、きちんと他者がいる。こういうの好きだなあと。堀自身が、『猶もこれ以上自分が作家として伸びられるかどうかの試練として、自分以外のものの真只中に自分自身を投げ入れて見ることの必要を痛感するようになってきた』(「覚書Ⅱ」新潮文庫版『菜穂子・楡の家』百八十五頁より)と述べている通り、菜穂子というヒロインは堀にとって、自分以外の存在として描かれている。堀の自我が満ちているように見える「風立ちぬ」より好きです。
6:確かにそうですね。小説の中で、明という青年は、ずっと一人で生きている。それに対して、黒川は、常に母と関係しながら生きている。そういう対比も、分かりやすいです。
イコ:黒川はマザコンなんですよね(笑)
◆菜穂子の心の動き
6:僕も「菜穂子」はまったく好きじゃないというわけじゃなくて、菜穂子の、心の動き、たとえば夫の黒川がやってきたときや、去っていった後など、黒川のことを考えるんだけど、つい明のことを考えてしまったりする。そういうところを興味深く読みました。
イコ:いいですね。菜穂子の心の動きといえば、好きなシーンがあります。新潮文庫版の『菜穂子・楡の家』の九十四頁なんですけど……。
6:あっ、同じですね。新潮文庫。
イコ:ほんとだ。あっ、やっぱり宮崎駿の「風立ちぬ」の帯が巻かれてる(笑)
6:これに合わせて買いましたからね(笑)
イコ:お互いに(笑)で、九十四頁の、青年と、重病の許嫁の出てくる場面です。青年がめっちゃ泣いてる。菜穂子は、許嫁が数日前から危篤に陥っていると知っていたから、やっぱり駄目だったんだな、と思うんですね。涙を死と結びつける。ところが実際は、許嫁が持ち直したから嬉しくて泣いてる(笑)
6:ありましたね。
イコ:それだけでもおもしろいんですけど、その後、事態は急変して、許嫁はやっぱり死んでしまう。青年は山を下りる。すると菜穂子は、なんかずっと重苦しく感じていたものから解放されたように思うんですね。えっ、それで胸の苦しさ、忘れ去られちゃうんだ、おもしろいな、と。
6:ふむふむ。
イコ:ああ死んじゃったんだ、次は自分かな、と書きそうなところを、あえて『重苦しいものからの釈放を感ぜずにはいられなかった。』(同九十五頁)と書く。これって、倫理的な観点でいえば、背徳的なものに見えるんですけど、菜穂子からしたら、療養所での孤独な生活の中に、浸っていたいんです。だから青年が嬉しくて泣いてる、っていうのは、なんとなく、自分の存在を否定されてるようで、嫌なんでしょう。許嫁が死んで、また孤独の中の自分が許される、そういう感情を描いているのは、すごいな、と思いました。
6:なるほど、そういう風に読めるわけですね。
イコ:他にも好きな場面がけっこうあります。
6:僕は、技師が山を下りるところが好きです。百一頁、退院していく患者が、治ったのではなくて、自分がしかけてきた研究を完成させるために独断で山を下りて行くんですよね。
イコ:その技師が後で、完治不可能な身体になって戻って来るんですよね。
6:ええ、あのくだりが好きです。時間の流れが感じられて。
イコ:先ほど黒川が、母と関係しながら生きているということについて挙げてもらいましたが、黒川が山に来て、菜穂子と一晩を過ごすところも好きです。黒川は療養所っていう非日常的な場所に来ることで、初めて母から離れて、菜穂子を直視する。でも、山から下りると、やっぱり母から離れられない……。
◆純愛の元祖?
6:堀辰雄は一九三〇年代に、文学青年の間で広く読まれていたそうです。
イコ:えっ、そうなんですか。なんか「ブルジョアの文学だ」と言われて、批評家の受けも悪かったようだし、今じゃ、あまり読まれていないように思いますが。小野寺さんによると、文庫にも長い間入らなかったみたいですし。
6:神風特攻隊に選ばれた文系学生がよく読んだ小説だと聞きました。それらの学生が、堀を読んでいたと思うと。
イコ:こういう男女の生活への、憧れもあったんでしょうか。
6:セカチューの話も出ましたが、堀辰雄って、純愛ブームの元祖みたいなところがありますよね。難病が出たりもする。
イコ:なるほど。堀作品の登場人物って、とにかく病気にかかりますね。「菜穂子」一作で見ても、菜穂子だけじゃなくて、明もそうだし、牡丹屋の、おようの娘も病気にかかってる。少しでもかわった様子が描かれると、この人も病気にかかってるんじゃないか、ひょっとしてみんな病気なんじゃないかと疑いたくなってしまいました(笑)それで、思ったのは、美しく生きようとすると、病気にかかるんじゃないかってことです。美しくっていうのは、自分の理想を通そうとする、自我をもった生き方って感じかなあ。
6:古くからに、「目病み女と咳取り男」というのがありますね。
イコ:どういう意味ですか。
6:目をわずらっている女はかわいく見えて、風邪をひいてごほごほ咳をする男は、かっこよく見えるものだっていう意味です。
イコ:へえ、目をわずらっている人? ちょっと嫌だなあ、それ。
6:病気の人と美しさが結びつくのも、そういう発想なのかもしれません。
(文責:イコ)
 twitter文芸部
twitter文芸部